理事長挨拶
西山理事長挨拶
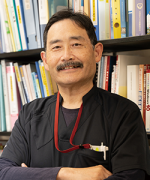
堀見前理事長のあと、2023年度より高知県腎バンク協会の理事長を拝命いたしました西山謹吾と申します。
私は救命救急センターで様々な救急医療の現場を経験してきました。その時初めて家族からの申し出で心停止下の腎提供に関わらせていただきました。それまでは大学病院に従事してきましたが、腎提供については携わることは皆無でした。腎提供を申し出られた家族と向き合う貴重な経験をさせていただき、それから数例腎臓・眼球の臓器提供に関わらせていただきました。そうしているうちに1999年には脳死下臓器提供に関わることとなり、脳死判定やドナー管理などいろいろ勉強させていただきました。その後は脳死下臓器提供の院内整備や研修会などを通じて活動してきました。
1997年「臓器の移植に関する法律」が施行されております。そこには第2条では基本的理念として「臓器提供に関する意思は、尊重されなければならない」、第3条では国及び地方公共団体の責務として「国民の理解を深めるために必要な措置を講ずるよう努められなければならない」と記載されています。したがって高知県腎バンク協会も移植(あるいは臓器提供)に対する国民の理解を深めていく様々な施策を行っていきます。
移植医療は、提供者(ドナー)と移植を受ける側(レシピエント)がいて成り立つ医療です。両者が十分納得した上で医療が展開されるように、私たちは心がけています。しかし腎提供に登録されてから移植に至るまで平均で15年前後(2023年)かかってしまうのはあまりに長すぎます。少しでも待機時間は短縮できるように、ドナー側となる医療機関の意識改革も必要でしょう。少しでも待機患者の待機時間を短くできるよう、また脳死下臓器提供が通常の医療の一部になれるように活動していきたいと思います。